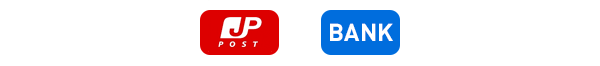逆境を乗り越えた人材が、同質化された社会に新たな価値観をもたらす
中川 亮平
長野県立大学グローバルマネジメント学部准教授
「あてもなく漂う蝶のようだった」“I was a butterfly floating in nothingness”
アンセルムは銃口を向けられ、絶体絶命だった。コンゴ民主共和国がまだザイールと呼ばれていた1990年代初頭のある日、首都キンシャサにある学生寮の部屋に兵士2人が突然押しかけてきたのだ。自分の権力が危険にさらされているという身勝手な強迫観念から、独裁者が知識層を粛清しようとしていた。同じ死ぬなら、こんな兵士に撃たれるよりも自分で死んだ方がましだ、とアンセルムはガラス窓を破って3階から飛び降りた。皮肉にも窓の下に横たわっていた仲間の学生たちの死体がクッションになり、彼は一命をとりとめたのだった。痛みをこらえ、死んだふりをしながら暗くなるのを待ってキャンパスを脱出し、貨物船に隠れてコンゴ川を上がり、トラックをヒッチハイクし、2つのジャングルの国境をくぐりぬけてケニアのナイロビに辿り着いた。
初めてホームレスになりバスターミナルで過ごした。3日目にはさすがに空腹に耐えられず、道行く女性に窮状をフランス語で訴えた。その女性は国連機関の職員でアンセルムの訴えを理解し、当時できたばかりのケニア東北部にあるカクマ難民キャンプに送られた。その頃隣国ソマリアなどでの政情不安から大量に難民が押し寄せており、ケニア政府は国民の支持を得にくい難民キャンプの設置を都市部からはるか離れた砂漠地帯に決めたのだった。昼の強烈な日差しと夜の冷えに耐え、栄養や衛生状態も悪くトイレすらなかった。体重も60キロから33キロに落ちた。テントの仲間たちが順々に死んでいく中、自分の番を待つような日々だったという。「地獄か当時かを選ばなければいけないのなら、地獄を選ぶ」とアンセルムは振り返る。
彼はそこで、他の難民たちが話すアラビア語と支援活動を行っていたNPO職員が話すスワヒリ語を耳で覚えてしまい、次第に両者の間に立つようになった。やがてNPOは彼の語学力と人柄に目をつけ、職員として採用した。アンセルムは死の順番待ちから離脱し、仲間の難民たちを支援する側に転向したのである。その数年後、NPOの幹部であった米国の大学教授がアンセルムの活躍と人柄に感銘を受け、教授が保証人となってアンセルムが難民の立場で米国に居住できるように取り計らってくれたのだった。この過酷な状況からアンセルムを救ったのは、コミュニケーション能力の高さ、世界中を一切敵にまわさない明るい人柄と、チャンスをくれたNPOや大学教授の存在だった。
教授のご縁で米国のアイダホ州に辿り着き、ビルの清掃の仕事をしながら英語をゼロから学びはじめた。そしてアイダホ州立大学を卒業し、米国籍も取得した。のち2001年8月から多額の借金を負ってでもコロンビア大学の修士課程で国際関係を学ぶためニューヨークに渡ったのは、アフリカの人々の自由と繁栄に少しでも貢献したいという熱意があったからだ。私がアンセルムに出会ったのはこの時期で、大学院に同期で入学し、大学が斡旋した2人用のアパートに偶々割り当てられたルームメイトだった。
大学院生活が始まって間もない9月11日(火)の朝、2機の旅客機がビルに突っ込むという惨たらしい事件がおき、ニューヨークはパニックに近い状態だった。それ以降、世界100か国から学生が集まる大学院では、どの授業でもいつもテロ事件のこと、その原因、その後の世界について自然発生的に議論・口論が沸き起こった。アンセルムとも毎晩午前2時3時まで、テロ事件のこと、世界の貧困や政治経済の問題、「小説より奇なり」な彼の壮絶な半生などをキッチンで語りあった。それまで日本でサラリーマン生活を送っていた私の感情の起伏など吹けば飛ぶようなものだったことを思い知らされ、恥ずかしくもなった。
硬直した同質に異質が「くさびを打ち込む」
強烈なほど異質な人々や価値観にさらされることで、私にとってそれまで空気のようなものだった日本の教育や社会の特異性がより際立って見えた。思い返せば、いわゆるエリートを生み出すための装置として、それはそれなりによくできていたと思った。私の育った時代はまだ高度成長期の名残で社会の合目的性が強く、支配する場の空気が強かった。またこうした同質を是とする仕組みは異質なものを排除しやすいか、あるいはあまり気に留めることがないシステムでもあった。
しかし、度重なる金融危機、玉石混交の大量の情報、地球規模での天災、各地の政情不安と難民の流出など、日本や世界を取り巻く情勢は目まぐるしく変わった。目に見えないウイルスに全人類がたじろいでもいる。今、数十年前の日本よりも社会の合目的性は弱まり、将来への不安は明らかに強いと思う。
それでも場の空気の支配は私の若いころと同様か、それ以上に強まっているのではないかと危惧している。沈黙の螺旋を促すような硬直な社会のままでは、不確定な変化に柔軟に対応できなくなる。社会がより寛容で柔軟になるために、私は以下の3点こそ将来世代の教育に、また全ての世代の心掛けとして重要であると考える。なお、これらは外国にあって日本にはないものだと訴えるのでは決してないことを付け加える。
1. 多面的な学び
事実はひとつでも複数の解釈があることを理解できるようになることを教育目標の一つとして据えるべきだろう。言い換えれば、事実に対する認識の枠組みは立場や状況に応じて異なり、変化もすることを認識するということである。そのためには建設的に批判し、批判されるトレーニングが必要だろう。このことは、偏見を減らすことや見えないものを見ない社会から脱却するためにも重要である。
2. 自己の尊厳と他者の尊重
これは多面的な学びにおいて他者や自己に対峙する時の態度のことである。多面的学びで意見交換をしながら自己の意見の相対的な位置を探る相互批判を行い、これを繰り返すことでアイデンティティが確立されていく。相互批判は他者を卑しめて自己の正当性を主張するのではなく、相手の意見を尊重して他者(の意見)の位置を確認することで自己を相対的に認める行為である。つまり、他者を認めることと自己を認めることは相互補完的である。これは民主主義社会の根幹であり、これからの時代は自己と他者の尊厳を認める教育が求められる。自己と他者の尊厳を認められれば、たいがいの人間同士の問題は解決することができるはずである。
3. 多様な相手との議論・協働
多面的に学んで自己・他者の尊厳を認めながら、多様な相手と徹底的に議論・協働をすべきである。そうすることによって、個人では発揮できない力を集団で発揮できる。個人よりも多様性のある集団の方が最適解を導く可能性が高いことについては、社会心理学の分野などで多くの研究がある。ただし、多様性が効果的に活かされるには集団における意見集約や情報共有の仕組みがあるかどうかに左右される。この点に関しては、たとえば現場の従業員も経営に対して発言することで企業のパフォーマンスが向上するということが労働経済学や組織行動論の分野で実証されている。つまり、互いのことをよく理解し十分に話し合うことで多くの問題は解決しやすくなるということである。また相互の信頼をベースに「くさびを打ち込む」発言をすることは、同調現象を抑止する効果もあることが心理学の分野において明らかにされている。
こうして組織や社会の不合理や不正義に「くさびを打ち込」み良い影響を与える人材として、他者の痛みを理解できる逆境を乗り越えた人こそ適任であると考える。こうした人は、他者への配慮をしながら発言ができる素質を既に備えているか、訓練によって得られるようになる可能性が高いだろう。
逆境を乗り越えた若者たちに機会を
アンセルムは大学院修了後、国連開発計画の職員としてニューヨーク、独立前後の南スーダン、モーリタニア、ガボンなどで主に人権保護活動に奔走した。現在は妻の地元アイダホ州のChildren’s Home Societyの事務局長として、健康・精神面で苦境にある子供たちやその家族を支援する仕事に日々奮闘している。彼はアフリカの同志のために活躍したいというビッグドリームを追うだけではなく、身近で困っている若者たちのために尽力することを厭わない。その原動力には、かつてアンセルム自身がケニアのNPOやアメリカの大学教授から恩恵を受けたことが根底にある。逆境を乗り越えた若者に機会が与えられることで、本人にも社会にも良い結果がもたらされることを行動で示すことを自分の使命と考えている。
日本でも逆境を乗り越えた若者たちにより多くの機会が与えられ、社会にも良い循環を作り出すことを推し進めたい。こうした若者こそ、硬直した組織や社会に「くさびを打ち込む」のに長けている可能性が高く、だからこそチャンスを与えられる社会システムが必要だ。特に不確実なこれからの時代にこそ、その重要性を強調したい。

中川 亮平
長野県立大学グローバルマネジメント学部准教授
東京三菱銀行(東京、京都)、American International Group(米国)、世界経済フォーラム(スイス)を経て教員に転身し、立命館大学、京都外国語大学を経て2020年より現職。経済・経営系の講義を行う傍ら英語によるカリキュラムの企画・設置準備・運営、キャリアセンター長、国際部長などを歴任。東京外国語大学ポーランド語卒業、コロンビア大学国際事情修士。